
公務員試験の面接で好印象を与える逆質問の具体例が知りたい

そもそも、逆質問ってそんなに重要なの?
「何か質問はありますか?」
面接官から最後にこう聞かれたとき、あなたはどう答えますか?
多くの受験生は、この質問を「形式的な質問」だと思い、無難な回答で終わらせます。
しかし実際には、この質問こそが合否を分ける「最後の勝負所」なんです。
準備不足の質問は志望度を疑われ、逆に的確な質問は「この人と働きたい」という決定打になります。
本記事では、今すぐ使える逆質問のテンプレ、市役所・県庁・特別区別の切り口、避けるべきNG例、さらに最後の一言まで完全解説しています!
読まなければ、せっかくの面接で評価を落とす危険があります。
ぜひ最後までご覧ください!
公務員試験の面接で「逆質問」が重要な理由
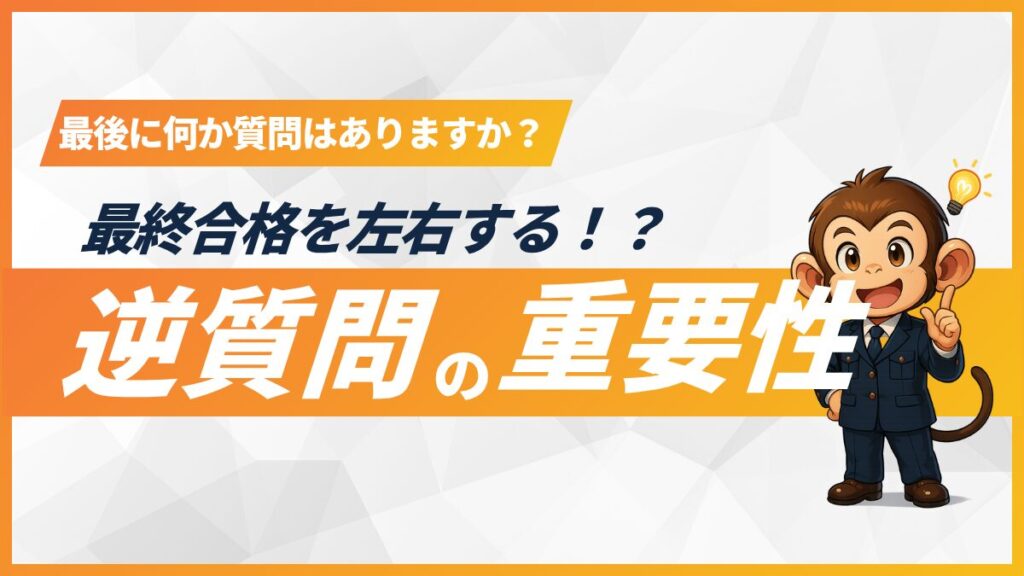
まずは、公務員試験の面接で逆質問がなぜ重要なのか?
ここから説明したいと思います。
公務員試験の面接における逆質問は、単なる形式的なやり取りではなく、評価を左右する重要な要素です。
なぜなら、面接官は逆質問を通じて、受験者の準備度・関心度・思考力を見極めているからですね。
事前に自治体や仕事内容を調べ、的確で具体性のある質問をすれば、熱意と理解度をアピールできます。
逆に無難すぎたり曖昧な質問は、評価アップの機会を逃してしまうことに。
つまり、逆質問は「印象を高める最後のチャンス」であり、事前準備と戦略が合否を分けるポイントになるんです。
面接官が逆質問でチェックしている3つのポイント

面接官は逆質問のどこをチェックしているの?
では、面接官は逆質問でどこを重要視してみているのでしょうか?
これは公務員試験の元面接官に聞いた話なのですが、面接官は主に以下の3点を見ているそうです。
- 事前準備の度合い:自治体や業務をどれだけ理解しているか。
- 志望動機の一貫性:質問内容が志望理由や自己PRと矛盾していないか。
- コミュニケーション力:相手の回答に対して適切に反応し、会話を広げられるか。
特に、1番目の「事前準備の度合い」は最重要です。
この3つを意識して逆質問を設計することで、受験者は「調べた知識」「志望への本気度」「会話力」を同時にアピールでき、総合評価の向上につながります。
ぜひ意識して作成してください!
逆質問をしなかった場合の評価や影響

逆質問をしなかった時の評価はどうなるの?
「特に質問はありません」で終えることは一見無難に見えますが、実際はマイナス評価となるリスクがかなり高いです。
面接官は、質問の有無から受験者の関心度や積極性を測ります。
何も聞かないと「準備不足」「熱意が低い」と受け取られる可能性が高くなります。
特に最終面接では、逆質問は自分を印象づける最後の機会です。
短くても構わないので、事前に用意した質問を一つは投げかけるようにしましょう!
公務員試験の面接で好印象を与える逆質問の具体例
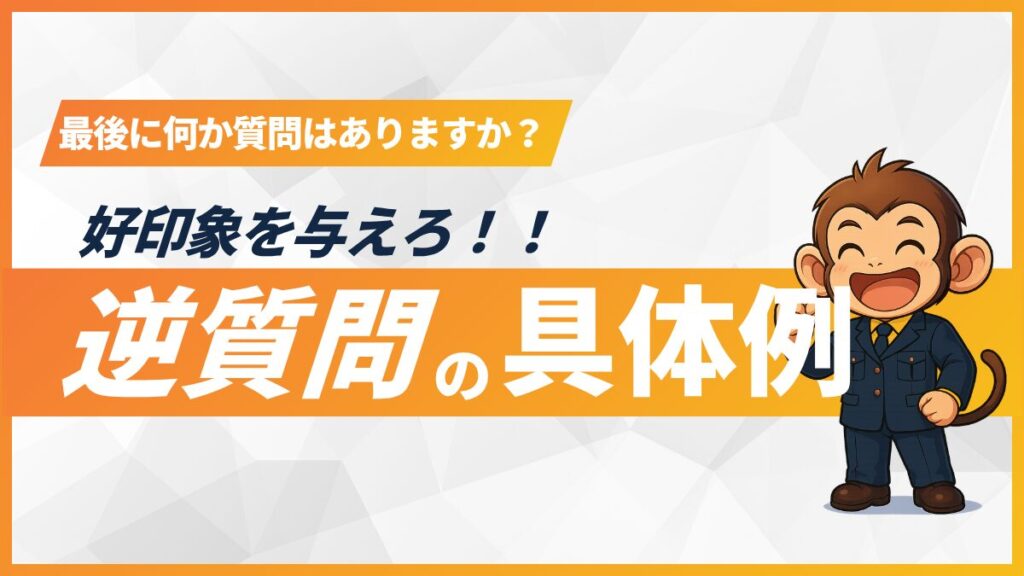
先述した通り、公務員試験の面接で逆質問を効果的に活用すれば
- 熱意がある
- 業務を理解している
- 準備を適切に実施できる
と印象づけられます。
では、どのような逆質問が効果的なのでしょうか?
面接官が「即採用したい!」と思う超具体的な逆質問の作成術やテンプレは下記記事にまとめているのでそちらをご覧ください。
ここでは、以下3パターンを紹介します。
- 汎用的に使える質問
- 志望動機と結びつける質問
- 会話を広げる質問
これらを事前に準備しておけば、どの自治体や試験種別でも安心して対応できます。
以下で具体的な例と使い方を紹介します。
汎用的に使える好印象な逆質問5選
多くの自治体で使える無難かつ印象の良い質問は、準備しておくと安心です。
これらは条件面に偏らず、業務や組織への関心を示せるため好印象です。
質問後は必ず面接官の回答にうなずきや感謝の言葉を添え、積極的な姿勢を印象づけましょう!
志望動機や強みと関連づける逆質問例
逆質問は、志望動機とリンクさせることで説得力が増します。
自分の強みや経験を踏まえて聞くことで、「自己分析ができている」「適性を活かす意欲がある」と評価されます。
質問は短く端的にし、回答後に意欲や関心を再度伝えると効果的です。
面接官との会話が広がる深掘り型逆質問例
会話を広げられる逆質問は、面接官との距離を縮める効果があります。
こういった質問は、面接官からの回答の幅が広がる質問です。
面接官が答えた内容に「それは○○という理由からでしょうか?」と続ければ、双方向のやり取りになり、受験者の関心と理解度を強く印象づけられます。
ただし、施策やサービスの内容について深掘りする質問をする際は、その施策・サービスを徹底的に調べておく必要があります。
面接官は現場で施策を実施している職員です。
深く突っ込まれた質問を投げ返された時に、答えに詰まってしまうと逆に評価を落としてしまう原因になります。
施策・サービス系の逆質問をする際は、しっかりと調べ上げるようにしてください!
試験種別ごとの逆質問例と注意点
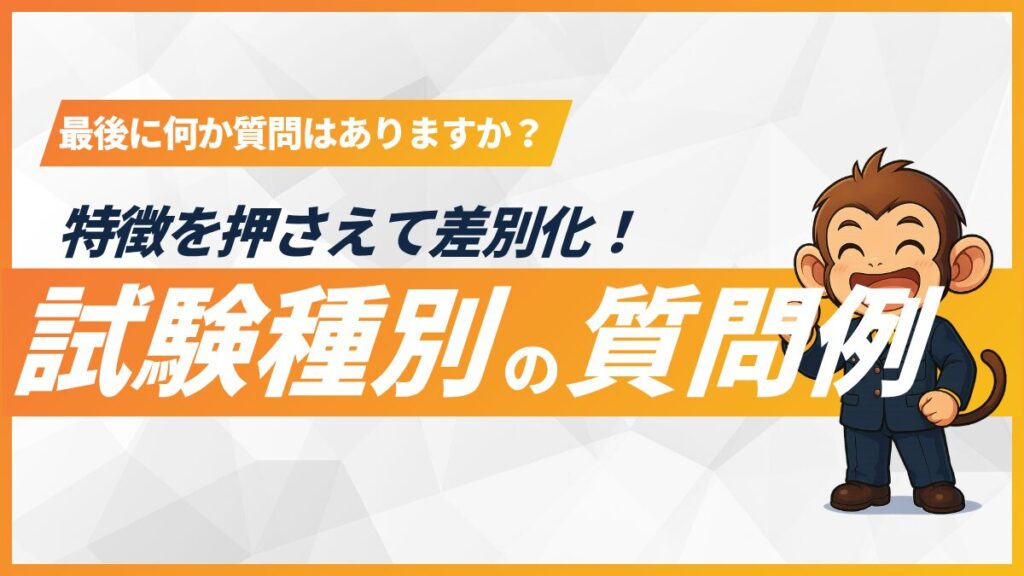
前章では、ある程度どの試験種にも使える汎用性の高い逆質問を紹介してきました。
ここからはもう一歩踏み込んで、試験種別に逆質問の具体的な例と注意するべきポイントを紹介します。
公務員試験の面接は、同じ逆質問でも試験種によって効果や印象が変わります。
- 市役所であれば地域密着性
- 県庁であれば広域的視点
- 特別区・政令指定都市であれば複雑な行政運営
それぞれ重視するポイントが異なるんですね。
逆質問も、その特性に合わせて準備することにより、的確に志望度や理解度をアピールできます。
ここでは試験種別ごとの具体例と注意点を解説します。
市役所面接で効果的な逆質問例と注意点
市役所面接では、地域とのつながりや住民サービスへの関心を示す質問が好印象です。
注意点は、事前に市の施策や広報資料を調べ、既に公表されている情報をそのまま聞かないこと!

そのまま聞いてしまうと「調べればわかるのに調べてないな」と事前準備の脆さが露呈してしまうよ!
しっかりと調べた上で自分の考えや具体性を加えるようにしましょう!
県庁で好印象を与える逆質問例
県庁では、広域的な視野と調整力が求められるため、政策全体や部局間連携に関する質問が効果的です。
注意点は、単なる施策の概要を聞くのではなく、自分が関わる可能性のある業務との関連を踏まえて質問すること!

自分の強みや将来関わりたい業務について話した上で、課題感や大変だったこと、意識した点を聞くと好印象でかつ自分の知識にもなっていくからオススメ!
特別区・政令指定都市面接での逆質問の工夫
特別区や政令指定都市は、人口規模が大きく、行政分野も多岐にわたります。
そのため、組織運営や現場課題に関する質問が有効です。
注意点は、広い業務領域の中で自分が特に関心を持つ分野を明確にした上で質問すること!
漠然とした抽象的な質問は印象が薄くなります。

特別区・政令指定都市を受験する方は、特別区・政令指定都市の役割や機能についてしっかりと調べた上で受験することをおすすめします!
地元以外の自治体を受験する場合の逆質問ポイント
地元以外の自治体を受験する場合、土地勘や地域課題、その自治体への関心や理解を示す質問が評価されます。
上記のように、地元ではない自治体を受験する場合は、事前調査の成果を盛り込むことが重要になります。
注意点は「なぜこの地域で働きたいのか」を裏付ける質問にすること。
単なる興味本位ではなく、将来の貢献意欲につながる形で質問すると、志望度の高さを強く印象づけられます。

自治体によっては、まだまだ地元の人優先で採用する傾向があるのでその辺りも情報収集しておくと良いよ!
公務員試験の面接で避けるべき逆質問NG例
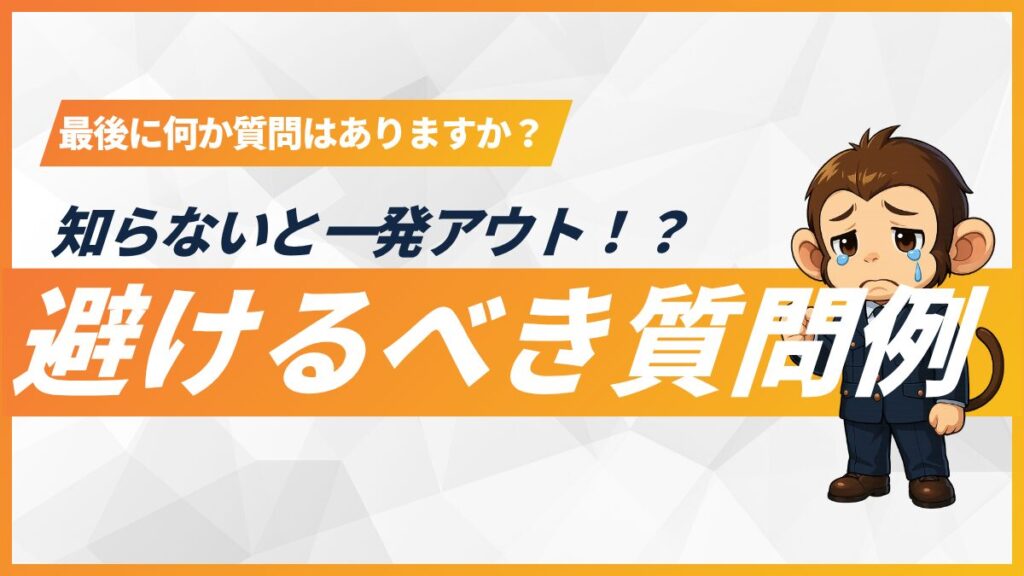
ここまで、効果的な逆質問を紹介してきました。
逆質問はチャンスである一方、質問内容を間違えると評価を下げる危険もあります。
特に、公務員試験の面接では「興味の方向性」や「情報収集の姿勢」がシビアに見られるため、NG質問は致命傷になりかねません。
ここでは代表的な3つのNGパターンと、回避するための視点を解説します。
代表的なNGパターンは以下の通りです。
- 調べればわかる質問
- 待遇や休日など条件面に偏った質問
- 面接官を困らせる曖昧・批判的な質問
それぞれ解説していきます。
調べればわかる質問
こうした質問は、公式HPや広報誌を見れば分かるため、面接官に「準備不足」と受け取られます。
避けるためには、調べた上での深掘り型質問に変えることが重要です。
- 事実確認だけで終わらないか?
- 自治体独自の取り組みや背景を絡められているか?
- 「知っている前提」で意見や感想を添えられるか?
待遇や休日など条件面に偏った質問
勤務条件に関心を持つこと自体は悪くありませんが、面接では「仕事より条件が優先」と見られ、マイナス印象につながりかねません。
条件面は採用後や説明会で確認するのが無難です!
- 面接で聞くべき内容か、それとも採用後でも分かるか?
- 条件面の話は「業務理解」や「自己成長」に絡めて質問できるか?
面接官を困らせる曖昧・批判的な質問
抽象的すぎる質問や、批判的に聞こえる質問は面接官は答えにくいです。
意図が伝わらないと「配慮がない人」と見られかねません。
公務員は市民を対象に仕事をおこないます。
市民に対しても、失礼な発言をしてしまうと捉えられるため改善するようにしましょう。
具体的には背景を示し、肯定的な方向に質問を導くことが重要です。
- 質問の目的が明確か?
- 肯定的・前向きな切り口で聞けているか?
- 相手が安心して答えられる内容か?
逆質問で失敗しないための3つのポイント

逆質問を成功させるためには、感覚や勘に頼らず、下記の3つのステップを押さえることが重要です。
- 事前準備
- 質問の具体化
- 当日の運用
この3つを意識すれば、どの自治体や面接官でも印象を損なわず、確実に評価を引き上げる逆質問ができます。
それぞれの対策ポイントについて解説していきます!
事前に質問リストを用意する
思いつきで質問をすると、内容が浅くなりがちです。
面接官は何百もの受験生をみているため、一発で見抜かれます。
事前に3〜5個の質問を用意しておくことで、緊張していてもスムーズに話せますし、事前に調べた上での質問になるので質問の質の担保もできるわけです!
- 自治体の公式HPや広報誌を調べたか?
- 自分の志望動機や強みと関連する質問か?
- 汎用・深掘り・志望動機連動型の3タイプを揃えているか?
【ミニテンプレ】
「○○を拝見して△△に興味を持ったのですが、□□についてもう少し教えていただけますか?」
自治体研究をベースに具体性を出す
抽象的な質問は印象が薄くなりがちです。
自治体の現状や施策を踏まえた「固有名詞入り質問」にすることで、準備度と関心の高さを同時にアピールできます。
- 固有名詞(施策名・地域名・事業名)が入っているか?
- 背景と理由を簡潔に添えているか?
- 答えやすい形に質問を整えているか?
例:「○○地区で進められている□□事業について、現場で感じる課題や今後の展望を教えていただけますか?」
自治体研究の効果的な方法についてはこちらをお読みください↓
質問の意図を明確にして話す
質問の裏にある意図を明確にし、面接官に「この質問は業務理解や貢献意欲につながっている」と感じてもらうことが大切です。
意図を含めることで、会話が広がりやすくなります。
- なぜその質問をするのか自分で説明できるか?
- 面接官の回答後に感想や追加の一言を添えられるか?
- 会話を一方通行で終わらせていないか?
例:「地域防災に関わる業務に興味があり、その準備段階で新任職員が担う役割を伺いたいです」
面接の最後に一言アピールする場合の例
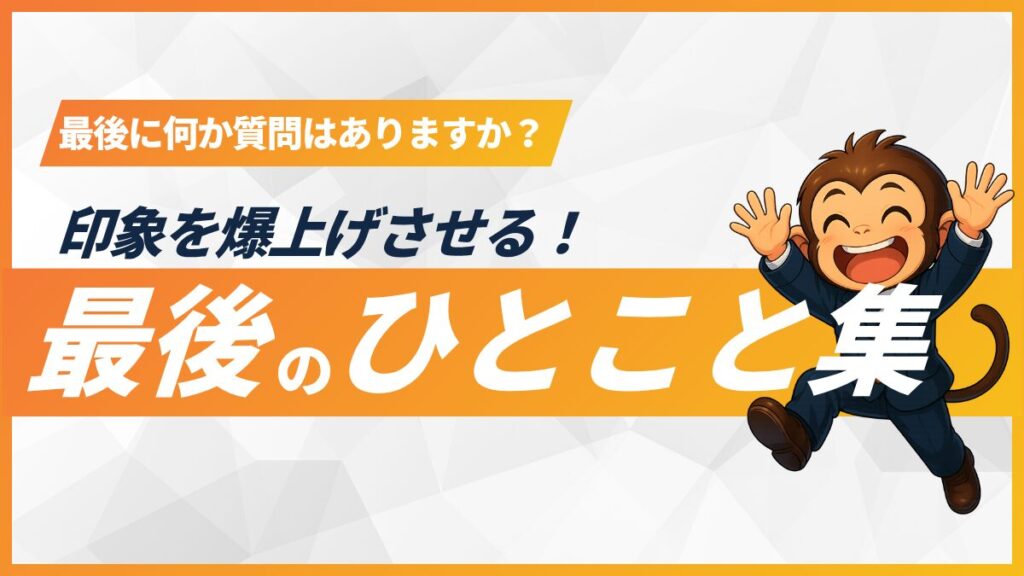
逆質問が終わった後の「締めの一言」は、面接官に残る最後の印象を決定づけます。
短くても、自分の熱意や貢献意欲が伝わる言葉を選ぶことで、面接全体がポジティブに締まります。
まさに「終わりよければすべて良し」ですね。
ここでは、感謝・志望度・意欲の3パターンに分けて例を紹介します。
感謝を伝える一言例
感謝を伝えて終える。
この流れは王道です。
面接官の時間と回答への感謝を伝えることで、礼儀正しさと人柄を印象づけられます。
ポイントは、具体的に「何が参考になったか」を一言添えることです。

いい一言が思い浮かばない人は感謝を伝えよう!
志望度を再度強調する一言例
最後に志望度を明確に示すことで、「この人は本気だ」という印象を残すことができます!
面接はいかに印象づけられるかが勝負です。
そういった意味では、かなりオススメの一言です!
短くても「具体的理由+働きたい意志」の2点を盛り込みましょう。
意欲や成長意欲をアピールする一言例
入庁後のビジョンや成長意欲を伝えることで、将来性をアピールできます。
将来性をアピールする受験生は少ないため差別化できる一言です!
面接官に「この人は伸びそう」と感じてもらうことができればグッと合格率を高められます!
【まとめ】逆質問は「調べたうえで、意欲を示す質問」が合格の鍵
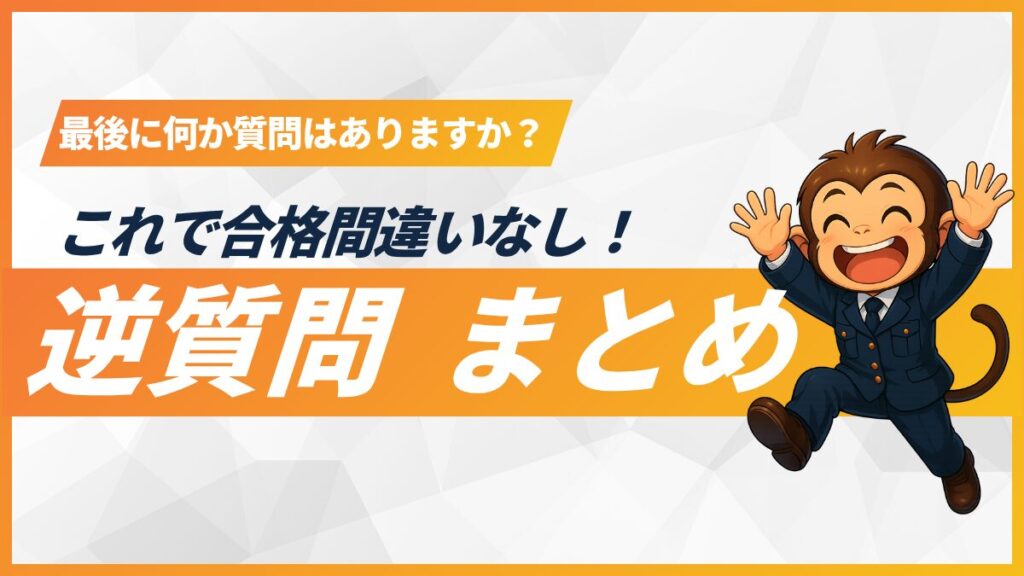
公務員試験の面接での逆質問は、単なる形式的なやり取りではなく
- 準備度
- 志望度
- コミュニケーション力
をアピールできる最後のチャンスです。
ポイントは、事前に自治体研究を行い「固有名詞+背景+意欲」を含む具体的な質問を準備すること!
そして、NG質問を避け、相手が答えやすく前向きなやり取りになるよう意識することです。
さらに、逆質問の後に感謝や志望度を伝える一言を添えることで、面接全体の印象がぐっと引き締まります。
面接は限られた時間の中で自分を最大限にアピールする場です。
この記事で紹介した逆質問の型やチェックポイントを活用し「この人と一緒に働きたい」と思わせる逆質問を作り上げてください!
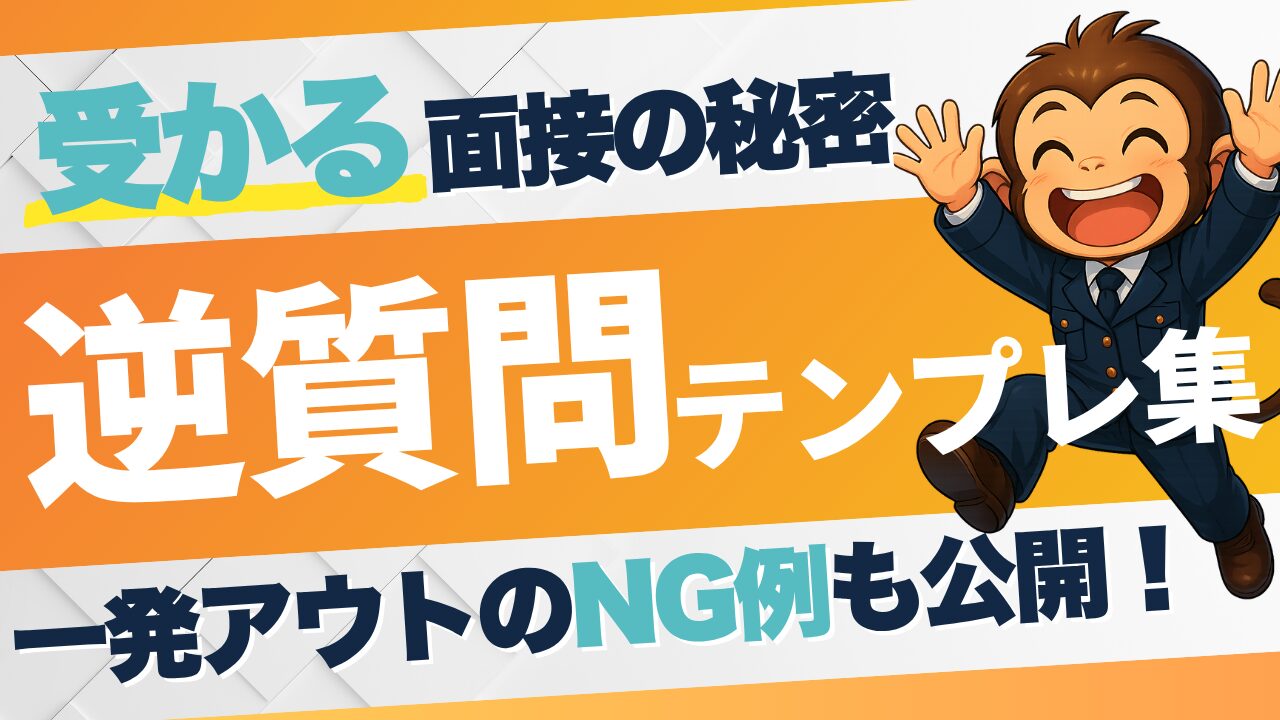


コメント